今回、花田伸一氏によって企画された分野横断的なビジュアルアートプログラムは、存在の美しさ、内面の在り方、そして人間の経験の普遍性について考察します。会期中6ヶ月間にわたり、4つの個展が開催され、内省への好奇心、自己変革から豊かな可能性まで、それぞれが精神の特異的な一面に捧げられます。このひとつひとつの個展において、県内の新しい声や著名な実践者を代表するアーティストとキュレーター間の共同作業による探求が繰り広げられます。
美観を超えて:「生」に美を見出す
全4幕の視覚の邂逅
2022年12月から2023年6月まで、イソップはこの地域初の直営店として長年親しんだ福岡天神の空間にて、 一連の展覧会を開催いたします。



今回の個展のインスピレーションはどこから得られましたか。 今回、僕達に与えられたテーマ「足元にある美」を考えた時に、キーワードとして現れたのが「拾う」という言葉でした。普段から川や海で採取した手のひらサイズの石に、小さい人体彫刻を取り付けた作品を制作しています。どこにでもありそうな拾った石から、唯一無二の石の風景がうまれます。何かを拾いテーマと場に繋げて展開することにしました。
今回のテーマはあなたにとってどのような意味を持ちますか。 「拾う」という言葉の意味の解釈から考え直すことによって世界の捉え方を再考する機会となります。
あなたの個展は本企画全体のテーマ(美について)とどのように繋がっていますか。 拾うという行為は能動的か受動的かと簡単に断言できない部分があります。それぞれの好みに左右される中動的な行いです。知識を持たない無垢な子供の段階に始まり、成長するにつれて段々とフィルターを通して物事を見分けるようになります。生きてゆく中で得たものを手放しては、自分なりの美を求め続ける。それが私たち人間の性なのだと気づく。固定化されない価値感こそ美なのではないか。そこが今回のテーマに繋がっていると感じます。
第3章-生島国宜

今回の個展のインスピレーションはどこから得られましたか。 イソップの旧店舗デザインが金属などの素材を生かしたとても個性的な内装で、私も素材感を全面に出した作品を作りたいと思いました。そこから油彩のほかに蝋、和紙、粘土といった素材を使うことに決めました。また、その内装デザインテーマが武士、武家屋敷のイメージということを聞いたので、かねてからテーマとしていた現代南画的なアプローチに至りました。
今回のテーマはあなたにとってどのような意味を持ちますか。
花田さんから個別に「委ねる・手 放す美」というテーマをもらい、私の活動や制作態度を理解してもらっているように感じました。美しくあるために思考を練り、手を加え続けるという作業は、時に徒労に終わります。シンプルで素材を生かしたものはそれそのもので美しいのですが、私の作品には自然な美しさに加え、人の営みのようなものを乗せたいと考えています。それは一般的には「美しくない」とされているものかもしれませんが、芸術作品とはそれすらもひとつのエッセンスとして「美≒Art」を形作ることができると思います。
あなたの個展は本企画全体のテーマ(美について)とどのように繋がっていますか。
世界は、それそのままで完璧で美しいと思っています。世界を美しく見れないのは、私自身に現実はこういうものである、こうあるべきだという考えが入り込んでいるからだと感じています。私を形作る考えを手放して、出来事に身を委ねる姿勢は究極的な美にたどり着くことではないかと思います。作品制作と発表はそのことを実践し、世界に問いかける行為です。
第2章-山内光枝
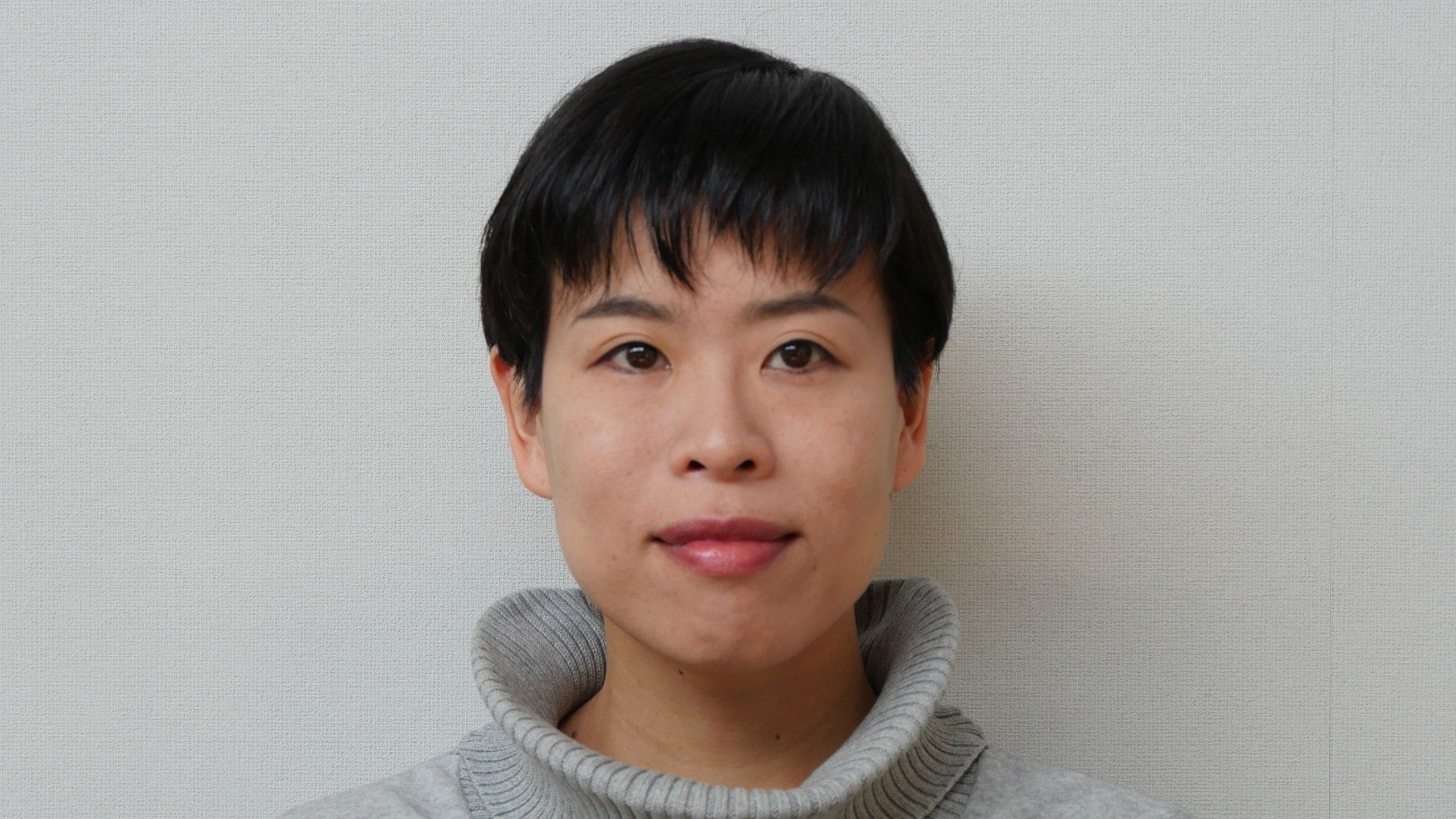
今回の個展のインスピレーションはどこから得られましたか。また、今回のテーマはあなたにとってどのような意味を持ちますか。
「同じ川に二度入ることはできない」 およそ2500年前に古代ギリシャの哲学者・ヘラクレイトスが述べたとされるこの一節は、さらにこう続いています: …なぜなら、川はつねに変化しているし 人もつねに変化しているからだ。
今回の個展では、展示会場の空間を織り成す鉄という物質の存在感、特に酸化現象を続ける壁面に着想を得て、世界(場)に生きて存在することそのものの流動性を空間全体で感じ、思考する場として提示することを構想しました。
つかみどころのない世界を認識しようとするとき、頭で理解しやすいように線を引いて二つに分けてしまいがちです。わたし/あなた、内/外、美しいもの/醜いもの。けれど私たちが日々生きながら体験しているのは、あらゆるものが関係しながら変化しつづけている、線の引けない世界に在るいのちという現象ではないでしょうか。私はこれまでも主に、海やそこに生きるひとびととの関わりのなかで、自ら引いた線に囚われた思考や認識を溶かしていく表現を模索してきました。
第1章-鈴木淳

今回の個展のインスピレーションはどこから得られましたか。
最初に「美」「遊び」というテーマがありましたので、そこを出発点としてイメージを展開しました。 「遊び」には「無垢」とか「無邪気」とか始原的な概念もあって、それを「美」として感じる価値観を私達は持っています。しかし、その「無垢」の持つ怖さというか危うさを、前々から感じていたので、それを問いかけるようなものにしようと思いました。
今回のテーマはあなたにとってどのような意味を持ちますか。
アーティスト(作家)として、非常に複雑なテーマに臨んだ実感があります。自分で設定したプランというかテーマでしたが、スリリングなものになったと思います。観る人に、複雑な問いかけをし、もちろん正解はありませんが、様々な事を考えたりイメージできるものになったと思います。
あなたの個展は傘となるギャラリーのテーマ(美について)とどのように繋がっていますか。
当たり前ですが、現代美術家として「美」は、私にとって重要なものです。それは「喜び」であり「幸福」であり「理想」でもあります。説明が難しいですが、「美」を「光」に例えるなら、「光」によって生み出される「影」があることも心に留めておきたいです。今回、そのことを再びあらためて考えることができました。ただ、そんなに大袈裟なことでなく、「美」も「世界」や「人生」同様、複雑なものだということでしょう。
花田伸一
キュレーターの 花田伸一氏は自己とその周りにあるものが調和することについて以下のように思索します。

本展覧会のテーマはどこからアイデアが湧いてきましたか。
今回のプロジェクトを企画するにあたり、抽象的な視点から「美」を見つめなおしたいと思いました。展示作品は、物質的な要素ではなく内面を掘り下げることで、内なる自分の複雑性をあらわにする場所に私たちをいざない、新しいものの見方を提示します。
今回のプロジェクトではどのようなアプローチを取られましたか。
本展覧会は大きく4つの章で構想されており、各章において福岡のカルチャーシーンとつながりのあるアーティストとキュレーターが協同して1つのテーマに向き合います。その中で、多様な視点と芸術的な表現手段を結びつけることで「美」の可能性を広げます。本展覧会を通じて人々が地域のアート エコシステムに関心を持ち、引き続き身近なギャラリーや美術館で創造的な探求の旅を継続していただきたいと願っています。
来場者にどのような体験をしていただきたいですか。
感受性よりも合理性や効率が優先される社会で、私たちはときに息苦しく感じることがあります。そのような中で、人は環境に対する無意識の反応として、自分の感情を抑圧してしまうかもしれません。私は自らの仕事を通じて、人々を内省へといざない、感覚に再びつながるための機会をもたらす、いうなれば単調な日々から抜け出すための回復体験としての芸術文化を探求しています。